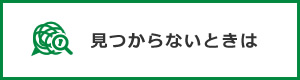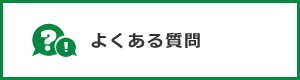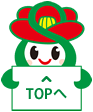町県民税(住民税)
町県民税は、一般には「住民税」と呼ばれ、「町民税」と「県民税」を併せたものです。実務上は町がまとめて税金の計算や賦課徴収をおこない、県民税分を納めています。また、町県民税は所得に応じて負担していただく「所得割」と一定の額を負担していただく「均等割」があります。
納税義務者について
1月1日現在、住所のある市町村において課税されます。
例えば4月に町外に住所を移した場合でも、その年は里庄町で課税されます。また所得証明の発行も同様ですので注意してください。
町県民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の所得金額が135万円以下
(給与所得者の場合は年収204万4千円未満)であった人
均等割がかからない人
前年中の所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者及び扶養親族がある場合には、その金額にさらに16万8千円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の人
所得割がかからない人
前年中の所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者及び扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の人
税金の計算方法
所得割の計算について
所得割の計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は所得税と同様10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。なお、住民税は前年中(1月1日から12月31日まで)の所得を基準として計算されます。
( 所得金額 - 所得控除額 ) × 税率 - 税額控除 = 所得割額
※所得の計算方法については、国税庁ホームページをご覧ください。
- 所得控除額には基礎控除、扶養控除や社会保険料控除等があります。ただし、控除額は所得税よりも低く設定されています。
(例えば基礎控除の場合、所得税だと48万円ですが町県民税は43万円の控除です) - 税率は、町民税6%、県民税4%です。
- 退職所得、山林所得、譲渡所得等は特別の税額計算が行われます。
均等割の計算について
令和6年度からは、町民税3,000円、県民税1,500円の合計4,500円です。(県民税1,500円のうち500円は「おかやま森づくり県民税」として、岡山県の森林保全のため負担していただくものです)
また、令和6年度から、国税である森林環境税1,000円を町県民税と併せて徴収することになりました。
町県民税の納め方
町県民税には納め方が3通りあります。
普通徴収
納付書または町指定金融機関からの口座振替により年4回(6月・8月・10月・1月)で納めていただく方法です。
給与からの特別徴収
年12回に分けて、給与からの天引きにより納めていただく方法で、給与所得者が対象です。この場合、給与の支払者が特別徴収義務者となり町へ納入します。
公的年金からの特別徴収
公的年金の支払いごとに、公的年金からの天引きにより納めていただく方法です。介護保険料が特別徴収されている年金所得のある人が対象です。この場合、年金の支払者が特別徴収義務者となり町へ納入します。